え~……こんなに「サイバーパンク2077」の記事を書いて騒いでおりますが、実は「サイバーパンク」そのものには、さほど興味なかったりします(汗)
というより、とりわけ「サイバーパンク」というカテゴリとして意識はしてこなかった、といいますか……。
そんなワケで、まずは「サイバーパンク2077」関係者が挙げた「ゲームタイトルに影響を与えたサイバーパンク作品」のことを。
それから、(サイバーパンクを意識してなかったけど)私が「読んで面白かったサイバーパンク作品」について書こうと思います!
あ、このへんでお断りしておきますが、この記事には多分に主観が含まれます。あと、敬称略です。ご了承ください。
サイバーパンクって何?
さて。
まず「サイバーパンクって何?」というところからですが、これはSFの分類のひとつです。
個人的には、「サイバーパンク」って「SF世界のハードボイルド」という感じです。かなり雑に言ってますが(笑)
特徴的な要素としては、「サイボーグに代表される、非常に発達した科学技術」「巨大都市(メガロポリス)」「ネットワークと人体の融合」「ディストピア」「暴力的かつ反道徳的な社会または階層」など……が挙げられると思います。
反骨精神(←パンク要素)が入るので、主人公は大体弱い立場の人間だったりします。
ジャンルとして主に1980年代半ばから1990年代の初めにかけて大流行しました。
以前も書きましたが、この頃の日本はバブル景気で非常に元気がありました。
これが、海外(特に欧米)の人の目には、脅威にも感じられたようです。
時代的な「日本脅威論」を色濃く反映しているのもサイバーパンクなので、往々にして日本企業や日本人が悪役として登場します。「サイバーパンク2077」も例外ではありません。
知りませんでしたが、「サイバーパンク」という言葉は、SF作家ブルース・ベスキ(Bruce Bethke)が1980年に発表した短編小説のタイトル「Cyberpunk」から来ているそうです。
「サイバーパンク2077」原作者が参考にした作品
「サイバーパンク2077」は、1990年に発売されたテーブルトークRPG「Cyberpunk 2.0.2.0.」をベースにしています。
また、「Cyberpunk 2.0.2.0.」には前作にあたる「Cyberpunk(2013)」が存在します。
これらを作ったのは、ゲームデザイナーの「マイク・ポンスミス」。原作者として、サイバーパンク2077の開発にも携わっています。
彼の最初の代表作は「Mekton」というロボットが登場するゲームで、漫画版「機動戦士ガンダム」の影響を受けているそうです。
なお、TRPG「サイバーパンク2.0.2.0.」の正統な続編として「Cyberpunk Red」というTRPGが発表されてもいます。

こちらの作品と「サイバーパンク2077」はリンクしているそうで、「サイバーパンク2.0.2.0.」と「サイバーパンク2077」の間を埋める作品のようです。
ファミ通のインタビュー記事によれば、原作者が『サイバーパンク2.0.2.0.』を作った当時に影響をうけた日本作品はなかったそうですが、今回「サイバーパンク2077」の開発にあたっては、「AKIRA」「カウボーイビバップ」「バブルガムクライシス」「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」からの影響を挙げています。
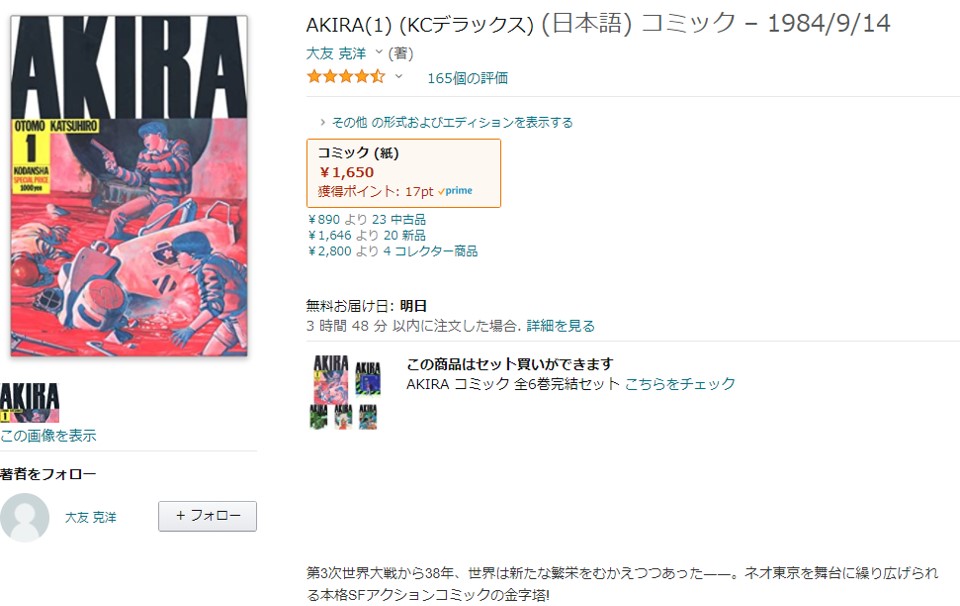
開発元CD PROJEKT Redスタジオの責任者JohnMamais氏のインタビュー記事をはじめ、色々なところで語られているのはとりわけ「攻殻機動隊」の影響で、ゲームに登場する「フラッドヘッド」という機械は「タチコマ」からインスパイアされたとも語られています。
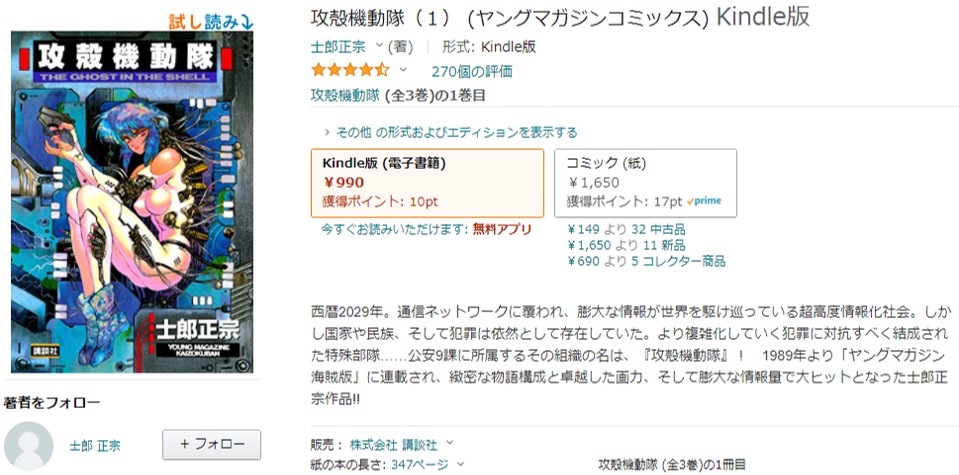
もちろん、映画「ブレードランナー」の名も挙がっていますし「押井 守作品」「今 敏作品」の言及もありました。
もっとも今 敏作品だと、「パプリカ」以外はあまりサイバーパンクと関連がなさそうな気もしますが……。
なお、映画「ブレードランナー」はフィリップ・K・ディック著「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」が原作ですが、原作にサイバーパンク要素はないようです。私も原作を読んでいるはずなのですが、そのへんはちょっと記憶にありません。
ニューロマンサー
「サイバーパンク」と言えば、ウィリアム・ギブソンによる長編SF小説「ニューロマンサー」を避けては通れません。

ゲームの影響で、Kindle版ではベストセラー1位を獲得していますね。
紙の本は960円(税込1056円)が定価です。今も新品が買えます。転売価格にご注意下さい。
出版されたのは1984年、日本で翻訳版が出たのは1986年のこと。
ネビュラ賞、 フィリップ・K・ディック記念賞、ローカス賞、ヒューゴー賞と、当時のSFの賞を総なめにしました。
サイバーパンクの起源とか始祖とか言われますが、とにかくこの作品の大ヒットが、「サイバーパンク」というジャンルとそのイメージを決定づけたのは、確かなことです。
メガロポリス「チバ・シティ」から物語は始まります。チバ・シティは「ナイトシティ」とも呼ばれています。
サイバーパンク2077に登場する都市の名も「ナイトシティ」ですね。
主人公ケイスはハッカーの仕事の失敗から、電脳空間にジャックインするコンピュータ・カウボーイとしての能力を奪われ、電脳空間へアクセスすることができなくなっています。
巨大電脳都市チバ・シティでくすぶっていたケイスですが、全身サイバネティクス技術で武装したストリート・サムライ「モリイ」という女から、能力を再生するのと引き換えに「やばい仕事」をもちかけられます。
電脳の世界に戻りたかったケイスはこの取引に飛びつきますが、やがて、陰謀と暴力に巻き込まれていきます。
……と、こう書くと何となく面白そうだと思うんですが、白状しますと、かつて購入はしたものの、最初の数十頁で挫折しております。文体が独特すぎて……(汗)
ただ、「ニューロマンサー」は三部作で、「カウント・ゼロ」「モナリザ・オーヴァドライヴ」と続きます。


「モナリザ・オーヴァドライヴ」は「ニューロマンサー」の続編という感じだそうですが、「カウント・ゼロ」は世界観は共通しているものの独立した物語らしいので、「カウント・ゼロ」に挑戦してもいいかなぁ……とは、思っています。
また、「ニューロマンサー」の元となっている作品として短編小説「記憶屋ジョニィ」があり、「クローム襲撃」という文庫に収録されています。短編の方がとっつきやすいかもしれません。
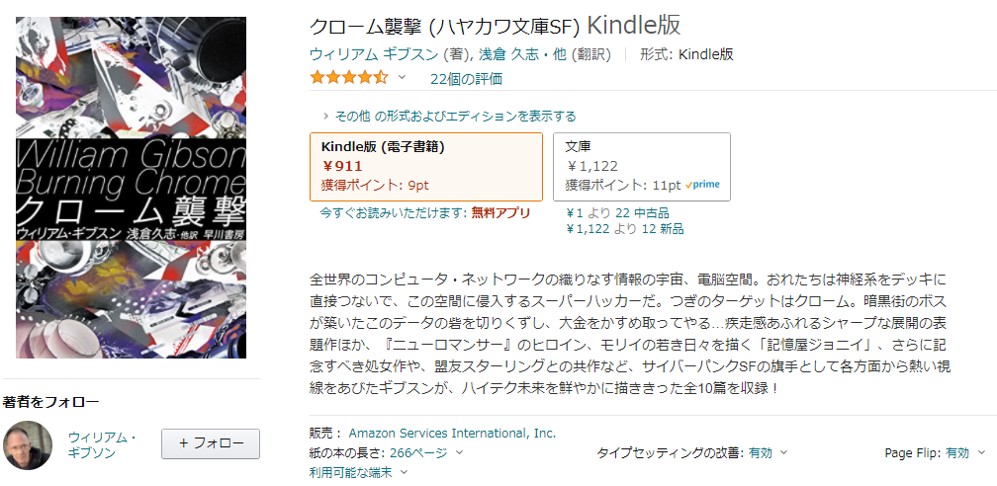
なお、「記憶屋ジョニィ」はキアヌ・リーブス主演で「JM」というタイトルで映画化もされました。
お勧めしたいサイバーパンク小説
さて、最初の方で個人的なサイバーパンクの印象を書きました。特にサイバーパンクに興味のなかった私のあのイメージはどこから来たものか、といいますと……。
柾悟郎「ヴィーナス・シティ」でほぼ形作られました。
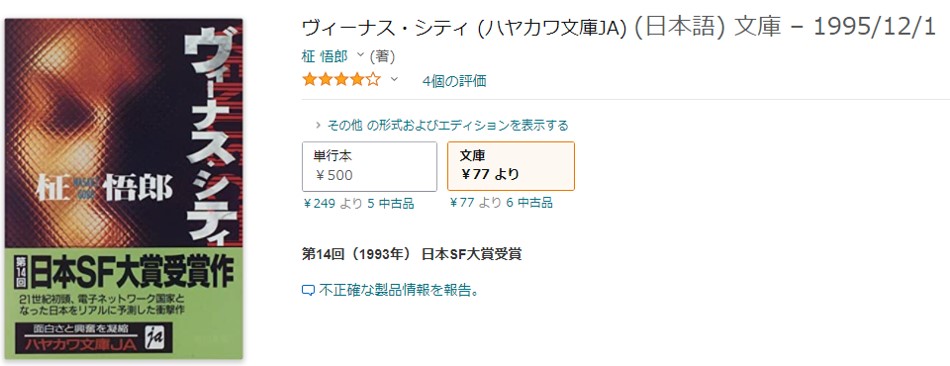
主人公は女性なのですが、ネットワーク上の仮想空間では両性具有になって活動しています。なので「サイバーパンク2077」で、プレイアブルキャラクターの性別は自由にカスタマイズできる、というニュースを見た時「ああ、ヴィーナスシティの世界だなぁ」と思いました。
で、もうひとつのおすすめは、冲方丁「マルドゥック・スクランブル」。
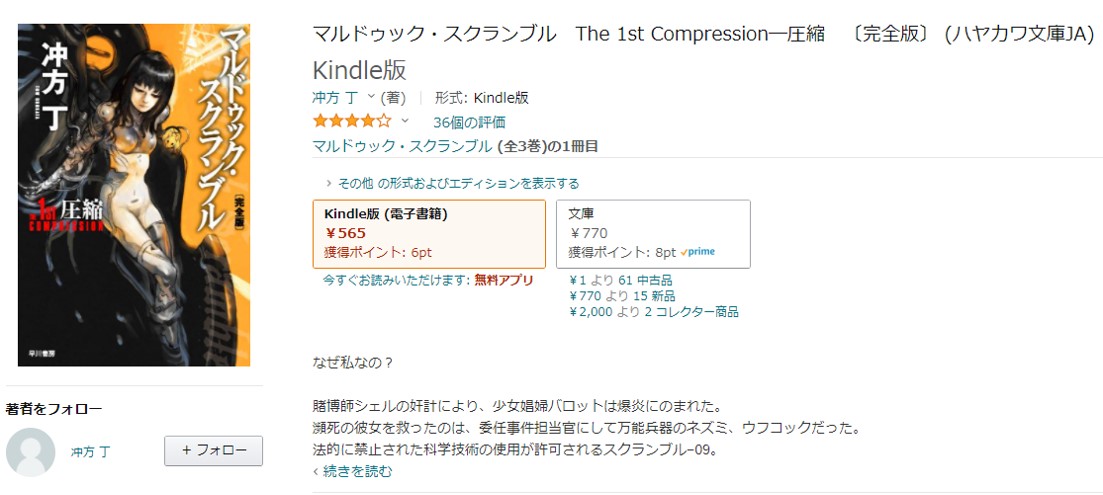
ただ、日本要素がなかったもので、当時「サイバーパンクとして」読んではいなかったのですがね……。
これらはサイバーパンクを意識しなくても楽しめる作品です。私がそうでしたから(笑)
あと、栗本薫作品にも影響を受けている気がするのです。が、タイトルが思い出せませんで……「レダ」だったかなぁ……ヒロインが好きじゃ無かったんですがね。

では、とりあえず、今回はここまで。
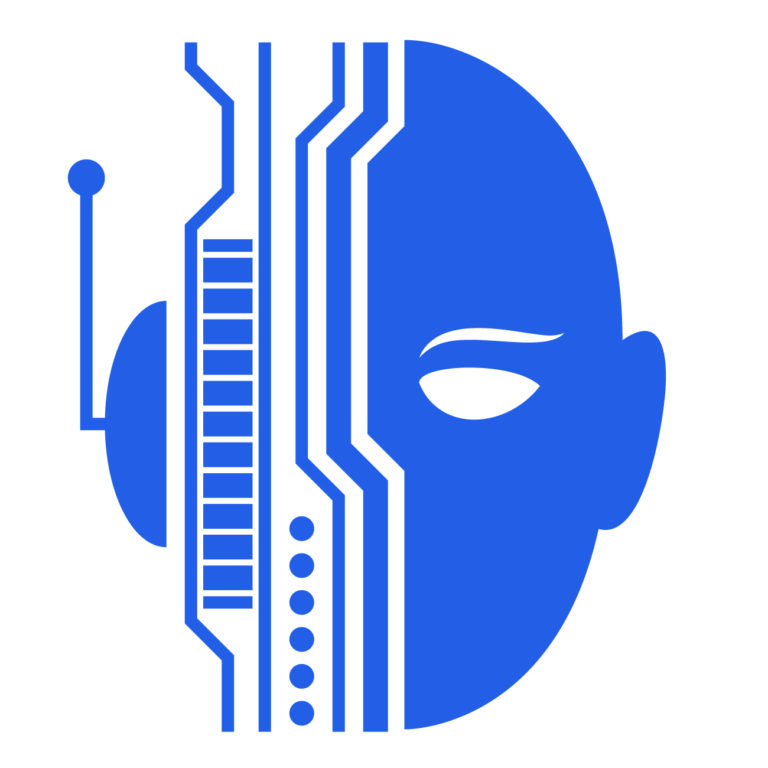



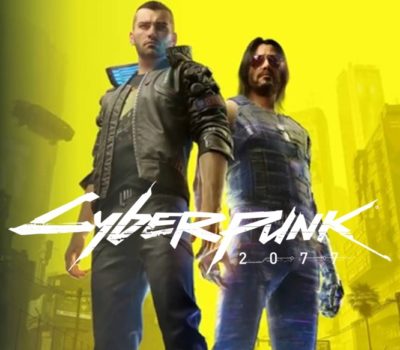
コメント